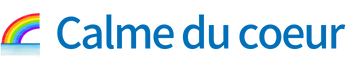「神経症」「うつ」「HSP」のお悩み克服 精神心理カウンセラーの堀川です。
今回は、「適応障害」について投稿させていただきます。
「適応障害」とは?
現代の精神医学上において「適応障害」は、生活をしていく上での、明らかなあるいはありふれた、出来事や変化などの心理的・社会的ストレスに対する不適応反応のことを表します。
適応障害の発症原因のいくつかの例として、職場環境の変化、職務不適性、パワハラ、退職、解雇、転職、入学、就職、引っ越し、死別、離婚、失恋、喪失体験、生命に係わる重大な疾患に罹るなどが挙げられます。
適応障害は通常、原因となる出来事や環境などの変化から1カ月以内に発症し、半年以上継続しないものとされていますが、あくまで私の個人的見解ですが、一年以上の長期に渡って継続することもあると思っています。
適応障害は、個人的な資質や性格、または精神的な脆弱性が、発症の要因および危険性と症状形成において、大きな要素を占めるとされています。しかし併せて、それと関係なく、その個人にとって適応障害と成り得るようなストレス要因がなければ、適応障害の状態には陥らなかっただろうとも考えられています。
「適応障害」の症状
適応障害の症状はさまざまですが、抑うつ気分・不安感・心配など、精神的な症状が主として出現します。
また、現在の状況のなかで対処方法を考え、計画的に行動することや持続することができないという感覚、日常生活上の日課や仕事の業務遂行などに支障が出ることも適応障害の症状の中に含まれます。
適応障害に悩まれる方の中には、過激な行動や衝動的な暴力行為を起してしまいそうだと感じる方もいますが、そのような行動を犯すことはほとんどありません。しかし、とくに青年期においてと言われていますが、症状が行為障害に結びつくことがあります。例として、攻撃的行為や非社会的行動が挙げられます。児童期では学校をサボる、暴力行為などの素行不良として現れることもあります。
職業領域(仕事や職場)においては、業務のボリュームや質、対人関係などに対して、うまく適応できない及び行動(言動)ができなくなり、また、ときには日常生活を送ることにも支障が出るようになった結果、適応障害と診断されます。
「適応障害」の対処方法
適応障害への対処方法であげられることとしては、まず環境調整があります。そして、それと併せて、適応障害になる要因の一つである、その人の持つストレス脆弱性や物事への対応能力(物事の捉え方や認識の仕方も含みます)を高めるようにすることが求められます。つまり、ストレス要因(→「ストレッサー」といいます)の軽減だけではなく、その人のストレスへの対応および対処能力を高めることへの視点が大切となります。
「適応障害」の定義など
上述のように適応障害は広い意味で表すと、さまざまな生活や職場、教育環境など(家庭、仕事、学校など)において、個人個人が持つ価値感による主体的な言動が、うまく周囲の環境と適応できず(調和できず)機能しなくなってしまった結果として、精神的・身体的・社会的に不都合をきたし、生きづらさを感じる状態であるということです。
また、米国精神医学会の診断マニュアルやWHOの国際疾病分類などでは、「適応障害」は以下のように定義されています。
①重大な生活上の変化もしくはストレスに満ちた生活上の出来事に対する適応の時期に発症する。
②個人の素質や脆弱性は、発症・症状形成に大きな役割を演じているものの、ストレッサーなしには適応障害は発症し得なかったと
考えられる。
③主たる症状は不安、憂うつな気分、行為の障害(無断欠勤、けんか、無謀運転など)であり、この結果、仕事や日常生活に支障が
生じている。
④これらの症状は、うつ病や不安障害など他の疾病の診断に該当するほど重篤ではない。
⑤発症はストレッサーの発生から1~3ヵ月以内であり、症状の持続は通常6ヶ月を超えない。
この定義をもう少し簡潔にまとめると、「適応障害」という疾患の概念は以下の4点になります。
①軽度な病的反応を引き起こすきっかけとなるストレス要因(ストレッサー)が存在すること
②ストレス要因(ストレッサー)に対する個人的な脆弱性や対処能力の問題(課題)が考えられること
③ストレス要因(ストレッサー)によって発生していると考えられる症状は重篤ではないが、正常的な領域を超えた
情緒的または身体的、行動上の障害が現実的に起こっていること
④ストレス要因(ストレッサー)の存在⇒その人個人のストレス脆弱性・対処能力の問題(課題)⇒ストレス状況(情緒的または身体的、行為の障害、そして、これらによる社会的運動機能の低下)」という一連の流れの間に関連性が認められること、ということです。
まとめ
精神医学上では、ストレス反応や適応障害は自然に治まることが多いと言われていますが、自分自身や周囲の対応の仕方によっては(適切な対応や対処策を取らないと)、精神面や身体面、行動面で異常な状態を繰り返したり、慢性化したり、神経症性障害(神経症)に発展する可能性もあります。ストレス要因(ストレッサー)に対する柔軟な適応力と抵抗力を身につけることも必要ですが、それが難しい場合は、ストレス要因(ストレッサー)を取り除く(ストレス要因から離れる)ような環境調整が必要になってきます。
精神科の薬物療法では、「対症療法」として抗うつ薬や抗不安薬が使用されますが、あくまで私自身の個人的な経験と考えでは「対症療法」のみでの完治は容易ではないケースもあると思っています。
今回の投稿は以上となります。
「あなたは独りではありません!!」
私と一緒に、「神経症」「うつ」「HSP」の悩みや生きづらさを克服しましょう!
無断引用&転載はご遠慮ください
Copyright©Calme du coeur All Rights Reserved.