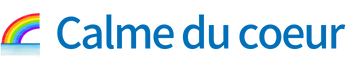森田療法について
森田療法は、1919年に日本の精神科医であった森田正馬(もりたまさたけ)が創始した、神経症に対する治療技法で、森田神経質などの神経症性障害の患者に用いられる、日本の伝統的な精神療法です。
森田療法では、神経症に悩む人は気質として神経質な性格傾向を持ち、何らかの誘因(何らかのきっかけや出来事)で起こる身体や精神の変化に敏感となり、意識が症状に集中し、それを取り除こうとするあまり、ますますその感覚が鋭敏となり、「とらわれ」という心理的な悪循環によって、「精神交互作用」と呼ばれる状態が生じると考えます。
そして、「かくあるべし」と考える理想の自分と「かくある」認めにくい認めたくない現実の自分との狭間の葛藤(「思想の矛盾」)により、症状への「とらわれ」が固着するとされています。
森田療法の治療は、まず症状を「あるがまま」に受け入れて、やるべきことを「気分本位」ではなく「目的本位」で患者に行動させることにより、あっては困るという「死の恐怖」を、よくありたいと思う「生の欲望」に転換させ、日常生活を通じて「あるがまま」の自分を受け入れて体得することを目標とします。
森田療法で行われる入院療法では、大きく4つの過程に分け実施されます。
第1期(絶対臥褥期[ぜったいがじょく])は、患者を個室に隔離し気晴らしになる活動を全て禁じ、食事・トイレ等以外は横になって過ごさせます。そうすることで、心身の疲れを取り払うと共に、精神的葛藤を軽減させます。次のステージの第2期(隔離治療期、軽作業期)では、個室での隔離は続けられますが、臥褥の時間を7~8時間に制限して日中は屋外で過ごさせるようにします。また、毎日日記を書くことで患者自身が自分の心身の状態を客観的に知るように指導します。さらに、起床時や就寝時に精神の活動を刺激するために古事記・万葉集などを音読させます。そして、次の第3期(作業療法期、重作業期)では、作業や読書を行わせ、最終ステージの第4期(日常活動訓練期)では、神経症の「とらわれ」からの解放と社会復帰を目指しての指導が行われます。
日本を代表する精神療法である森田療法ですが、現在は神経症にとどまらず、うつ病やうつ状態、心身症、がん患者のターミナルケアやメンタルヘルスの向上などにも幅広く活用されています。
Copyright©Calme du coeur All Rights Reserved.