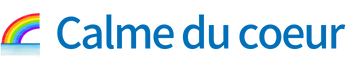「神経症」「うつ」「HSP」のお悩み克服
精神心理カウンセラーの堀川です。
今回は、「パニック障害」の「パニック発作」について、
その定義を追記させて頂きたいと思います。
「パニック障害」で悩まれている方はもちろんのこと、それ以外の方もお読み頂ければと思います。
「神経症」には実に様々な症状があり、それぞれの症状で多くの方が悩んでらっしゃいます。
ご自身が悩んでらっしゃる「神経症」の症状以外の症状に対する知識を深めるのはとても大切なことです。
その理由は、当時の私もそうでしたが、「神経症」の苦しみの真っ只中のときは、自分の症状の辛さ苦しみだけに意識が向き、
それが負のスパイラルを招き、そして症状が固着していくからです。
そこで、他の症状についても理解を広げることで、悩んでいるのは「自分だけではない」と、視野を広げる一助になります。
前置きが長くなりましたが、「パニック発作」の定義について見て行きましょう❗
「パニック発作」は、
DSM-IVにおいてはっきりと定義されています。
DSM-IVという単語を初めて耳にする方も少なくないと思います。
DSM-IVは、アメリカの精神医学会が作成した「精神疾患の診断・統計マニュアル」のことを指します。
DSM-IVでは、精神疾患ごとに診断基準の項目が規定され、その基準数を超える項目が揃ったときに、
どの精神疾患に該当するかが判断されます。
では、DSM-IVでの「パニック発作」の定義とはどうか見ていきましょう❗
DSM-IVでは「パニック発作」は、『強い恐怖または不快を感じる、はっきり他と区別できる期間で、そのとき以下の症状の中で
4つ(またはそれ以上)が突然現れ、おおむね10分以内にその症状が頂点に達する場合』を、「パニック発作」と定義しています。
【チェック項目】
1.動悸、心悸亢進、あるいは心拍数の増加
2.発汗
3.身震いあるいは震え
4.息切れ感あるいは息苦しさ
5.窒息感
6.胸痛あるいは胸部不快感
7.嘔気あるいは腹部の不快感
8.めまい感、ふらつく感じ、頭が軽くなる感じ、あるいは気が遠くなる感じ
9.現実感の消失、あるいは離人症状
10.コントロールを失うことに対する、あるいは気が狂うことに対する恐怖
11.死ぬことに対する恐怖
12.異常感覚(感覚の麻痺)
13.冷感あるいは熱感
いかがだったでしょうか?
今回は、「パニック発作」を主観的ではなく客観的に見る意味合いで、投稿させて頂きました。
今回の学びは以上になります。
次回は「全般性不安障害」について投稿させて頂きます。
精神的な悩みを抱えているのは、あなた一人ではありません❗
森田理論を学び実践すれば、必ず改善します‼️し、治ります‼️
私と共に一歩一歩学んで行きましょう🎵‼️